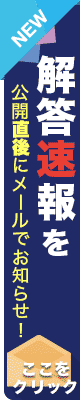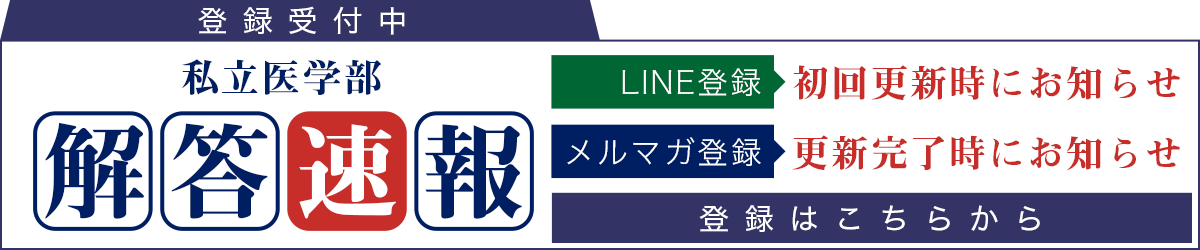【2026年】藤田医科大学の解答速報・過去問解答
【2026年度】藤田医科大学の各科目講評と全体統括
推薦(ふじた未来入試)
英語
今回の入試は、形式に関して昨年度から大きな変化はありません。第1問の文法・語法4択は、熟語や文法知識を試す標準的な良問でした。第2問の語句整序も同様に、基本的な知識と応用力が求められ、副詞句の位置など、際どい判断が必要なものも含まれました。第3問の長文は「人間の文化を動物の文化と差別化する要因としての『無制約性』」に関する英文で、設問数は少ないものの、確実に答えるには全文を読む必要があり、速読力が問われます。第4問の長文は「若者に広がる『問題のある』ソーシャルメディア利用」に関する英文で、話題が身近で取り組みやすい問題でした。第5問の長文記述問題は「アルツハイマー型認知症に関するリスク評価を受け取るか否かに関する研究」に関するもので、設問指示が明確なため、根拠さえ見つけられれば説明を仕上げるのはさほど難しくありませんでした。第6問の英文中英訳問題は「ドラゴンマンがデニソワ人と特定されたことのもつ意義」に関する英文からの出題でした。基本的な知識で文構造は構成できるものの、英文中から利用できる単語は少なく、適切な単語を選択できるか、修飾要素をうまく組み込めるかで得点に差が出ます。全体として、比較的得点しやすいマーク式を素早く正確に処理し、後半の記述式問題にどれだけ時間を捻出できるかが総得点の鍵となるでしょう。これまでの出題傾向通り、処理力、思考力、表現力がバランスよく求められています。目標は65%です。
数学
今回の入試の難易度は、昨年度と比べると問題1の小問集合では上がり、問題2と3の記述問題では下がりました。小問集合では易しい問題が減り、経験を要する標準レベルの問題が多くなったため、結果として点差がついたと思われます。中には、数学IIIの知識を用いると簡単でも試験範囲に則ると難しくなる問題など、工夫が必要なものが含まれていました。ここで7題程度を正解できるかが勝負の分かれ目です。問題2の「図形と計量、平面図形」は、二等辺三角形と円に関して余弦定理などを用いて線分長を求める問題で、方針さえ立てられれば完答が望まれますが、差がついている可能性もあります。問題3の「場合の数、数列」は、数え上げや重複組合せの典型的な問題が出題され、非負整数を用いる有名なテクニックも知っておきたいところです。昨年度に比べると問題2と3の難易度は下がっているため、このうち少なくとも一方は満点に近いところまで仕上げたいところです。また、本学の特徴であった証明問題が出題されていないことは注目すべき点です。目標は70%です。
総評
今年度のふじた未来入試は、形式は大きく変わらないものの、限られた時間内での取捨選択がより重要となった入試でした。各科目とも、安定して得点できる部分を確実に処理しつつ、時間を要する設問にどれだけ回せるかが合否を分けます。
全体として、処理力と判断力、そして答案をまとめ切る力を総合的に発揮できた受験生が有利になる構成でした。
LINE・メルマガ登録で全科目閲覧可能
↓登録はこちらから↓
理科3科目については、LINE・メルマガ登録後に送られるメッセージ内URLをご確認ください。
【メールが届かない場合】迷惑メールに振り分けられている可能性があります。迷惑メールフォルダをご確認いただくか「mebio.co.jp」の受信設定をお願いいたします。
【大学別】 解答速報・過去問一覧
【2025年度】藤田医科大学の各科目講評と全体統括
前期
藤田医科大学医学部 一般選抜(前期)入試データ
| 年度 | 志願者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 繰上げ合格者数 | 合格最低点 | 入試科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,301 | 421 | 120 | - | 571/800(1次) | 英、数、理(2)、面接(MMI含む) | 英200、数200、理200、面接40(2次) |
| 2024 | 3,492 | 431 | 120 | - | - | 英、数、理(2)、面接(MMI含む) | 英200、数200、理200、面接40(2次) |
| 2025 | 3,108 | - | 120 | - | - | 英、数、理(2)、面接(MMI含む) | 英150、数150、理200、面接40(2次) |
総括
志願者数: 2025年度の志願者数は3,108名であり、過去2年間と比較して減少しています。2024年度からは384名減少しています。 1次合格者数: 2023年度は421名、2024年度は431名でしたが、2025年度のデータは現時点では公表されていません。 最終合格者数: 過去3年間とも120名で変化はありません。 繰り上げ合格者数: 過去3年間のデータは見当たりませんでした。 合格最低点: 2023年度の1次試験の合格最低点は800点満点中571点という情報があります。2024年度、2025年度のデータは見当たりませんでした。 入試科目・配点: 過去3年間で入試科目と配点の大きな変更は見られません。1次試験で英、数、理(2科目)が課され、2次試験で面接(MMI含む)が評価されます。
まとめ
藤田医科大学医学部一般選抜(前期)の2025年度入試では、志願者数が減少しました。最終合格者数は過去3年間で一定ですが、1次合格者数や合格最低点の最新データは公表されていません。入試科目と配点については大きな変更はないと考えられます。志願者数の減少が、競争率や難易度にどのような影響を与えたかは、今後の情報公開を待つ必要があります。 より詳細な分析や最新の情報については、必ず藤田医科大学の公式ウェブサイトの入試情報を確認してください。
英語
文法問題や語句整序問題は標準的な良問です。第3問の長文は「子どもが食物アレルギーを発症する原因となる遺伝子変異」に関する英文でした。遺伝子変異とそれによる疾患の発症という、ある程度受験生にとってなじみのあるトピックですが、確実に答えを出すには全文に目を通すことが必要で、速読力が問われます。第4問の長文は「他人の手を握る行為に対する前頭前皮質の反応」に関する英文でした。文章内容は標準的ながら、やはり確実に答えを出すには話の流れをしっかりつかむ必要がありました。第5問の記述長文は「太陽フレアの証拠となる極付近の樹木に残された炭素14」に関する英文でした。根拠となる箇所さえ見つけられれば、説明として仕上げるのにはさほど苦労しない設問となっていました。第6問の英文中英訳問題は「オメガ3脂肪酸が健康に与える影響」に関する英文からの出題でした。本文から拾える表現があり、文構造も平易で迷うところはないものの、下線部は昨年度よりも長くなりました。基本的な語彙力で差がつくでしょう。目標得点率は60%です。
数学
2025年度は、形式面の変化はありませんでしたが、難易度は小問・大問ともに例年より大きく易化しました。また、数学Ⅲの微積分からの出題が極端に少ないことも特徴的です。問題1はどの設問も落とせません。問題2は数学Ⅱの微積分の典型題であり完答が望まれます。問題3の整数問題は現場対応力が問われますが、なるべく高得点がほしいところです。目標得点率は75%です。小問対策として、演習を通してマークならではのテクニックを身に付けること、また大問対策として、典型的な証明問題の比重を大きくしておくことがポイントです。
物理
2025年度前期は昨年度前期よりやや難化しました。大問は4題で、剛体のつりあい、ニュートンリング、質量分析器、衝突の問題が出題されました。大問1・2は基本的な問題で、確実に得点したい内容でした。大問3は標準的な内容ですが、見慣れない設定が含まれ、運動量と力積の関係を使えるかどうかが鍵となりました。大問4は立式自体は難しくないものの、計算が煩雑で慎重な作業が必要でした。時間内に全問解くのは厳しいため、目標得点率は60%です。
生物
昨年同様、大問3題構成で、良問ではあるもののやや難しめの出題が多く、身につけた知識をいかに使いこなせるか、という本質的な力が問われています。出題テーマは、「ヒトの生殖・心臓」「染色体の構造と変異」「酵素」で、どの大問もいわゆる典型題とは少し異なる問い方になっていますが、教科書的な知識の本質的な理解と、それを発展させる読解力・応用力があれば、きちんと正解に辿り着くことができる設計になっています。質・量ともに非常によく練られた秀逸な出題で、実力差がきれいに反映されたでしょう。全体的な難易度は高いため、目標は55%です 対策としては、まずは教科書的な知識の精度を上げること、そしてその知識を正しく運用する技術を身につけることが求められます。一つひとつの問題を解くことが他の知識への発展や応用へとつながるような、質の高い演習を積んでおきましょう。また、例年は「個体群・生態系」といった分野からの出題も多いので、苦手な分野を作らないようにしましょう。
後期
藤田医科大学医学部 後期入試データ
| 年度 | 志願者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 繰上げ合格者数 | 合格最低点 | 入試科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 約64名 | - | - | 英、数、理(2)、面接(MMI含む) | 英200、数200、理200、面接40(2次) |
| 2024 | - | - | 約63名 | - | - | 英、数、理(2)、面接(MMI含む) | 英200、数200、理200、面接40(2次) |
| 2025 | - | 少数 | 約60名 | - | - | 英、数、理(2)、面接(MMI含む) | 英150、数150、理200、面接40(2次) |
総括
志願者数: 正式な志願者数はまだ公表されていません。 1次合格者数: 2025年度の1次合格者は少数であったとの情報があります。 最終合格者数: 過去2年の最終合格者数は60名台で推移しており、2025年度も約60名程度と推察されます(メルリックス学院の情報による)。 繰り上げ合格者数: 正式なデータは公表されていません。後期入試は繰り上げ合格が発生する可能性がありますが、人数は不明です。 合格最低点: 公式な合格最低点は公表されていません。 入試科目・配点: 前期と同様、1次試験で英、数、理(2科目)が課され、2次試験で面接(MMI含む)が評価されます。配点も同様です。
まとめ
藤田医科大学医学部後期入試は、募集人数が非常に少ないため、依然として狭き門であると考えられます。最終合格者数は例年60名台で推移しており、2025年度も同様の傾向が見られます。1次合格者は少数であったとの情報から、1次試験の難易度が高かった可能性も考えられます。合格最低点が非公表であるため、具体的な難易度については不明です。 正式なデータや詳細な分析については、必ず藤田医科大学の公式ウェブサイトの入試情報を確認してください。
英語
2025年度前期と大問構成は変わりません。第3、4問の長文については、ある程度全体を見回さないと設問に答えを出しにくいものとなっています。第5問の記述問題は答えを出しやすい設問になっており、全体としては前期よりも取り組み易いでしょう。目標は65%です。
数学
2025年度前期と比べると、小問集合、大問ともにやや難化しています。小問集合は,計算が面倒だったり,ショートカットのテクニックを知っていると有利となる問題が含まれ、差がつきやすくなっています。大問は、整数問題の方は比較的穏やかな出題でしたが、値の評価に関する問題の方は,方針の策定と計算がいずれも重く、苦戦した受験生が大半だったと思われます。目標は60%です。
物理
2025年度後期は昨年度後期より易化しました。力学の大問は2題とも解きやすく、取りこぼしを避けたい問題でした。熱の問題は計算が煩雑になりやすく、時間を取られた受験者も多かったと考えられます。電磁気の問題は標準的な内容ですが、問6はやはり計算力が求められる問題でした。例年出題されていた剛体の出題がなく、全体的に解きやすい問題の割合が多めでした。目標得点率は75%です。
化学
2024年度後期と比較して大問数は7つから6つに減ったものの、題の難易度が上がっていたため全体としての難易度はほぼ変わらない内容でした。時間的に厳しい分量だったため見直しに時間を割けた受験生は少なかったと予想される分、少なくとも第1問や第2問など難易度の低い設問をミスなくクリアする必要がありました。その上で残る問題の出来不出来で差がつく勝負となったでしょう。一次合格の目標は 65 % です。
生物
前期同様、大問3題構成で、内容的には前期試験よりはやや取り組みやすい出題が多くなっているため、目標は75%です。 出題テーマは「骨とカルシウムイオン」「バイオームと生態系」「免疫」です。一番難易度が高かったのは、第2問の「バイオームと生態系」の問題で、多くの受験生が学修を後回しにしがちな分野であることに加え、グラフ図を丁寧に理解しておぼえていることが求められており、かなり得点しにくかったでしょう。第1問の「骨とカルシウムイオン」の問題は、一つひとつの設問は難しくないものの、分野横断的な内容であるため、それぞれ分野においてどれだけ丁寧に学修を積み重ねてきたかで差がついたでしょう。第3問の「免疫」の問題は、この中では一番オーソドックスな内容ですが、知識の正確な運用力が求められています。後半の「沈降線」の問題は、類題を解いた経験があったかどうかで差がついたでしょう。 対策としては、やはりまずは教科書的な知識の精度を上げること、そしてその知識を正しく運用する技術を身につけることです。一つひとつの問題を解くことが他の知識への発展や応用へとつながるような、質の高い演習を積んでおきましょう。また、やはり「個体群・生態系」の分野からの出題が多く、難易度も高いので、これらの分野を敬遠せず、しっかり攻略しておきましょう。
\私立医学部大学別模試一覧はこちら/