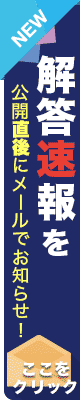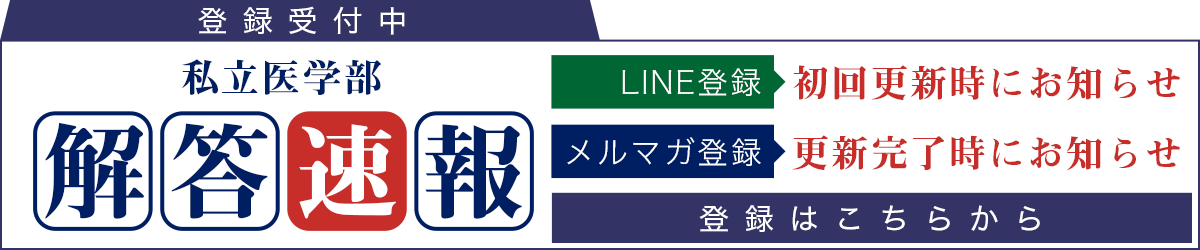【2026年】東海大学医学部の解答速報・過去問解答
LINE・メルマガ登録で全科目閲覧可能
↓登録はこちらから↓
理科3科目については、LINE・メルマガ登録後に送られるメッセージ内URLをご確認ください。
【メールが届かない場合】迷惑メールに振り分けられている可能性があります。迷惑メールフォルダをご確認いただくか「mebio.co.jp」の受信設定をお願いいたします。
【大学別】 解答速報・過去問一覧
【2025年度】東海大学医学部の各科目講評と全体統括
1日目
東海大学医学部 一般入試(A方式)入試データ
| 年度 | 試験日程 | 志願者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 繰上げ合格者数 | 合格最低点 | 入試科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2日開催 | 3,078 | 800 | 130 | 多数 | - | 英、数、理(2)、小論文、面接 | 英100、数100、理200、小論文・面接- |
| 2024 | 2日開催 | 3,035 | 800 | 130 | 多数 | - | 英、数、理(2)、小論文、面接 | 英100、数100、理200、小論文・面接- |
| 2025 | 2日開催 | 2,757 | 800 | 130 | 多数 | - | 英、数、理(2)、小論文、面接 | 英150、数150、理200、小論文・面接- |
総括
試験日程: 過去3年間とも2日間の日程で開催されています。 志願者数: 2025年度の志願者数は2,757名であり、過去2年間と比較して減少傾向にあります。2023年度からは321名、2024年度からは278名減少しています。 1次合格者数: 過去3年間とも800名で変化はありません。 最終合格者数: 過去3年間とも130名で変化はありません。 繰り上げ合格者数: 過去3年間とも「多数」としか公表されておらず、具体的な人数は不明です。 合格最低点: 非公表のため、比較できません。 入試科目・配点: 過去3年間で入試科目と配点に変更はありません。1次試験で英、数、理(2科目)が課され、2次試験で小論文と面接が評価されます。
まとめ
東海大学医学部一般入試(A方式)は、過去3年間とも2日間の日程で開催されています。2025年度の志願者数は減少しましたが、1次合格者数と最終合格者数は過去3年間で一定数を維持しています。合格最低点が非公表であるため、難易度の変化を断定することはできませんが、志願者数の減少は競争率の緩和に寄与した可能性があります。試験日程が2日間であることは、受験生にとって体力的な負担も考慮する必要がある点です。 より詳細な分析や最新の情報については、必ず東海大学の公式ウェブサイトの入試情報を確認してください。
英語
大問構成,問題量及び難易度のいずれも例年並みです。試験時間・問題量を考慮すると,処理速度が要求されますが,マーク式問題は語彙問題や会話問題の一部を除けば総じて基礎的・標準的なレベルの問題が多いので時間を費やしすぎず,最終的に合否を分けることが予想される記述問題にしっかりと時間をかけたいところです。目標得点率は75%です。
数学
2024年度に数学IIIが含まれなくなり,それ以前よりも問題が易しくなりましたが、今回のセットはさらに易しくなっています。ただし分量はやや多いので,処理力が得点を大きく左右するでしょう。目標得点率は80%です。
物理
2025年度は昨年度よりやや難化しました。大問は4題で、弾性力や摩擦力の運動、質量分析器、平面波の干渉、気体の状態変化が出題されました。大問1・2は典型問題で、確実に得点したい内容でした。大問3・4は後半の計算がやや煩雑で、特に大問4では状態変化の過程を正しく読み取る必要がありました。時間配分を意識することが重要で、目標得点率は65%です。
生物
2025年度1日目は解答の形式が記述式からマーク式に変わりましたが、大問数や出題内容に大きな変更はありませんでした。大問は例年通り5題が出題されており、代謝、生態系の物質生産、霊長類の進化、変異原性、免疫と進化から出題されました。全体としては昨年より易化しました。大問4・5は問題文や設問の日本語にわかりにくい箇所が多く、問題を解く作業に加えて問題文の解釈にさらに時間を取られた受験生が多かっと思われますので、比較的得点しやすい大問1・2・3でいかに取りこぼしがなかったが重要でしょう。目標得点率は65%です。
2日目
英語
大問構成,問題量はいずれも例年並みです。マーク式問題は語彙問題や会話問題の一部を除けば総じて基礎的・標準的なレベルの問題が多いですが、大問7,8がやや難化したため、目標t得点率は65%です。
数学
今年度は2日続けて大問で図形の要素が多く含まれていました。1日目に比べるとこの2日目の方がやや解きづらい問題構成でした。小問集合で5問程度を正解した上で、大問2、大問3でどれだけ処理しきれたか、という勝負になるでしょう。目標得点率は70%です。
物理
2025年度2日目の難易度は1日目と同程度で、昨年度2日目とも変わらないレベルでした。大問は4題で、万有引力、RLC並列交流回路、音波のドップラー効果、気体の状態変化が出題されました。大問1・4は比較的解きやすく、大問3(5)は難しい問題でした。大問2は未知の素子を扱う交流回路の問題で、難易度が高く、類題を経験していない受験生には厳しかったでしょう。全体的に作業量はそれほど多くなく、目標得点率は65%です。
生物
2025年度1日目は解答の形式が記述式からマーク式に変わりましたが、2日目は大問3のみ昨年度までと同じく記述式でした。大問は例年通り5題が出題されており、発生、物質輸送・遺伝暗号、免疫、血糖調節、食虫植物の進化・PCR法から出題されました。全体としては1日目よりやや易化しました。大問1・2は比較的得点しやすく、残りの大問にも得点しやすい問題が散りばめられていましたので、そこで取りこぼしなく得点を稼ぐことができたかどうかが重要でしょう。目標得点率は70%です。